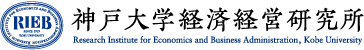グローバル金融研究部門
グローバル金融研究部門について
金融のグローバル化および金融市場の統合が急速に進む中、わが国および世界経済において、バブルや金融危機に対してどのような政策をとるべきか、また教訓を活かして再発を防ぐことができるか等を理論的、実証的および制度的に先端的研究を行います。さらに、地域レベルでの金融の役割についても研究します。内外の研究者との共同研究を中心に、国際金融政策、国際通貨システム、ミクロ政策分析、およびマクロ政策分析の4研究分野で総合的に取り組みます。

研究分野
国際金融政策
グローバル経済下における金融政策の果たす役割を学術的に分析し、そして政策提言につながり得るような研究に結びつけることを目指します。理論的な研究としては、危機への対応として主に新興市場について、どのような政策が望ましいか金融政策を中心に分析を行います。実証的な研究としては、計量経済学及び時系列分析手法を応用することで、金融政策効果及び政策対応に関する分析を行います。
国際通貨システム
国際通貨・金融システムに関する理論的・実証的・制度的研究を中長期的な研究課題とします。具体的には、グローバル・インバランス(世界的な経常収支の不均衡)問題、基軸通貨ドルに代わるSDR(特別引出権)を拡充した国際通貨システムの構築、および通貨危機やグローバル金融危機の再発防止のための国際通貨基金(IMF)などを中心とする国際金融アーキテクチャー、ギリシャを発端とする欧州通貨危機などについて考察します。
ミクロ政策分析
日本の金融政策の内、金融市場を円滑に機能させるための政策に焦点を当て、定量的・定性的な分析を加えます。具体的には、①地域金融システムと金融システム政策、②中小企業金融と信用保証制度、③公的金融の役割、④商品先物市場の役割などを検討します。その際、金融システム政策のあり方を、利用者サイドおよび供給者サイドの両方の視点から実証的に検証し、また、金融政策当局者や金融機関の経営者との意見交換を踏まえながら、エビデンスベースの政策提言を行うことを目指します。そのために、内外の研究者や実務家との研究交流の場として、金融システム研究部会を運営していきます。
また、上記の論点は、歴史的経緯を踏まえた検討がなされるべきであり、我が国に組織的な金融市場が誕生した江戸時代から現代までを、通史的に把握することを目標に掲げます。すなわち、江戸時代大坂の両替商と大名の間に成立した融資契約の実態把握(①に対応)、江戸幕府が財政難に苦しむ大名に提供した公的金融制度(②・③に対応)、そして世界初と言われる堂島米会所における先物取引の機能分析(④)などについて分析を進め、現代のミクロ政策分析との接続を図ります。
マクロ政策分析
マクロ経済における資産バブルの発生・崩壊、バブル崩壊が引き起こす金融・経済・財政危機、および他国で発生した金融・経済危機がマクロ経済に与える影響を分析し、グローバルな視点から、バブル期・金融危機・財政危機時に有効な経済政策を考察・提言します。さらに、通貨のバブルとも言えるデフレーションや為替の高騰に関しても、バブル的現象であるとの観点から理論化を図ります。
研究者一覧
| 職位 | 研究者 | 研究分野 | 主な研究課題 | 個人ページ |
|---|---|---|---|---|
| 教授 | 上東 貴志 | マクロ政策分析 | 動的最適化とマクロ経済動学 | リンク |
| 教授 | 北野 重人 | 国際金融政策 | 国際資本移動グローバル化の影響と政策のマクロ的分析 | リンク |
| 教授 | 家森 信善 | ミクロ政策分析 | 日本の金融システム政策の実証研究 | リンク |
| 教授 | 柴本 昌彦 | 国際金融政策 | 計量経済学・時系列分析を応用した日本経済の実証研究 | リンク |
| 准教授 | 髙槻 泰郎 | ミクロ政策分析 | 前近代経済の時系列データを用いた計量分析と日本の金融市場を対象とする制度分析 | |
| 准教授 | 明坂 弥香 | ミクロ政策分析 | 選好パラメターの形成・変化、夫婦の労働供給、大学専攻の男女差 | リンク |
| 講師 | 松井 暉 | ミクロ政策分析 | デジタルプラットフォーム上の人間行動のメカニズムの解明 | |
| 特命講師 | 荻巣 嘉高 | マクロ政策分析 | マクロ経済学、労働経済学、ネットワーク科学 |