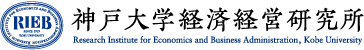所長からのご挨拶

神戸大学経済経営研究所は、1919年に設立された神戸高等商業学校商業研究所を起源とし、経済学と経営学の両分野を掲げる唯一の国立大学附置研究所として、106年の歴史と伝統を誇ります。現在、小規模な部局ながら、日本学術会議会員・連携会員8名を擁し、経済学の国際ランキングであるRePEcで国内4位にランクインするなど、先端的な研究を展開しています。当研究所では、学術研究を通じて新たな知識の創出に貢献することを目指し、以下の取り組みを重点的に進めています。
まずは、国際共同研究の推進です。これまで韓国の漢陽大学校やシンガポールの南洋理工大学と毎年共催で国際シンポジウムを開催していましたが、参加大学が増加し、より多くの国から研究者が集まるようになっています。また、本研究所が刊行する『The Japanese Accounting Review』主催の国際カンファレンスには、世界中から多くの研究者や大学院生が参加しています。さらに、これらの活動以外にも、国際シンポジウムやセミナーを積極的に開催し、海外の研究者との交流を深めています。加えて、2024年にはインド工科大学デリー校との学術交流協定も締結するなど、国際共同研究は年々増加しています。
二つ目は、産官学連携を通じた外部機関との連携強化です。産官学連携は大学の重要な役割の一つであり、社会科学分野でも積極的に進められています。当研究所では、長年にわたり神戸商工会議所との共催で「神戸経済経営フォーラム」を開催しており、最近ではさまざまな企業との共同研究も行っています。また、地域共創研究推進センターを設立するなどし、中央政府や兵庫県、神戸市など地方公共団体との連携も強化しています。研究者と実務家の関心を結びつけ、その成果を実務に還元する産官学連携は、本学の理念である「学理と実際の調和」にも合致しています。
三つ目は、計算サーバーを活用した文理融合研究の推進です。AI(人工知能)の発展により、機械学習やビッグデータを活用した研究の重要性が経済学や経営学にも高まっています。これらの研究を進めるには計算サーバーの活用が不可欠でありますが、当研究所ではその起源を戦前の神戸商業大学商業研究所時代の経営機械化研究における機械計算機の利用に遡ることができます。さらに、所内の計算サーバーをGPU(グラフィックス・プロセッシング・ユニット)搭載のものに更新します。このように、社会科学における機械学習やビッグデータ活用のための土壌や基盤は整っており、それを活かして文理融合研究を積極的に推進していきます。
最後は、歴史的企業史料の整備と公開です。当研究所では、明治から昭和初期にかけて国内最大の企業だった旧カネボウ株式会社の鐘紡資料や、大同生命保険株式会社のルーツである豪商・廣岡家に関する廣岡家文書など、貴重な企業史料を所蔵しています。これらの史料は近代日本の経営や金融を理解する上で重要ですが、経年劣化が進んでいるため、デジタル化が急務です。人的・金銭的リソースには制約がありますが、整備と公開を進め、それらを活用した研究の促進にも努めます。
大学を取り巻く環境は年々厳しさを増していますが、今後も当研究所の強みを活かし、神戸大学らしい研究拠点として発展できるよう努めてまいります。皆様のご支援を心よりお願い申し上げます。
2025年(令和7年)4月1日
神戸大学経済経営研究所長 西谷 公孝