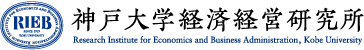RIEBセミナー
RIEBセミナー
(科研基盤研究 (B)「中世畿内における経済力の再検討」/六甲フォーラム共催)
RIEBセミナー
科研基盤研究 (B)「中世畿内における経済力の再検討」/六甲フォーラム共催
| 日時 | 2024年11月23日(土) 15:00 - 17:00 |
|---|---|
| 会場 | 神戸大学経済経営研究所 会議室(研究所新館2階) |
| 対象 | 教員,院生,および同等の知識をお持ちの方 |
| 使用言語 | 日本語 |
| 参加登録 | ※事前登録制です。下記より参加登録をお願い致します。追って、詳細をご連絡いたします。 参加登録 締切:11/17 |
15:00 - 17:00
- 論題
- 南蛮貿易への日本人による投資構造
- 報告者
- 岡 美穂子(東京大学史料編纂所)
- 概要
- 本報告では、ポルトガル人が主体でおこなったと考えられてきた「南蛮貿易」の資本の構造を詳細に検討する。「南蛮貿易」は、基本的にはカピタン・モールと呼ばれる、軍事的恩賞などでポルトガル国王により日本航海の権利を与えられた艦長が統率するものであった。しかし実際には、数種の特定商品の取引独占権がカピタン・モールに与えられたものの、船上の商品の大半は貿易に参加する個々の商人たちに属した。中国産の生糸に関しては、コンメンダ型の資本集約の構造が見られた。日本人商人や為政者たちは、希望の商品を買い付けるためにこれらのポルトガル人商人に資金(銀)を委託することで、南蛮貿易に参加し始めた。戦国時代は大友宗麟、豊臣秀吉等、江戸時代に入ってからは家康はじめ主に西国の諸大名たちがこの貿易に「出資者」として参加している。これらの委託銀は当初純粋な商品購入のために充てられたが、ある時期から高利と海損補償を伴う「冒険貸借(海上銀)」の条件を持つケースも現われ始めた。報告者はこの転換の契機が1609年のノッサ・セニョーラ・ダ・グラッサ号(通称マードレ・デ・デウス号)事件であったと考えている。ここでは南蛮貿易全体の変遷を辿りながら、その運営資金の在り方の変化を探り、この貿易における日本人の主体性に光を当てたい。