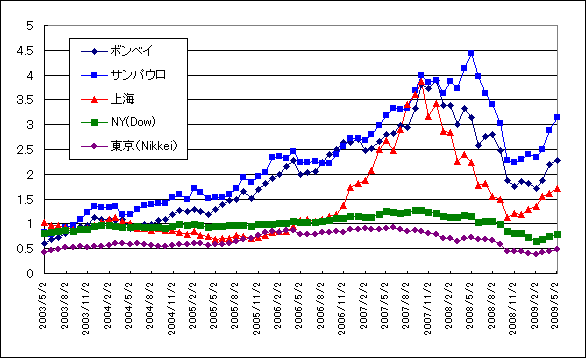
世界に台頭するブラジル経済−「未来」は現実となりつつあるのか−
神戸大学経済経営研究所
教授 西島章次
1940年代、オーストリア出身の作家シュテファン・ツヴァイクがブラジルを「未来の国」と呼びその将来性を予見した(もしくは現状を嘆いた)が、あたかもその「未来」が現実となりつつある。1980年代には超インフレと対外債務危機によって深刻な経済状況に陥ったが、1990年代に入ると経済自由化を実施し、それまでの政府介入の経済運営から市場メカニズム重視へと劇的な転換を遂げ、ブラジル経済はこれまで経験したことのない成長経路を歩み始めている。
ブラジルでは1994年の「レアル計画」によって懸案のインフレが終息し、1993年に2500%に達していたインフレ率は2008年には6%にまで低下した。また、経済安定化とともに、貿易・資本自由化、民営化、規制緩和などの経済自由化によって、その経済・ビジネス環境が一変し、貿易や直接投資が急増している。例えば、ブラジルの輸出は変動相場制に移行した1999年以降急増し、2000年の551億ドルから2008年には1979億ドルと4倍近く増加している。ブラジルへの直接投資の増加も顕著で、1995年の44億ドルから2000年の328億ドル、2008年の451億ドルとなり、途上国のなかでは中国に次ぐ2位、3位の直接投資受入国となっている。とくに、欧米企業が工業部門のみならずサービス部門にも積極的に進出し、様々なビジネス展開によってブラジルの活力を高めている。
さらに、特筆すべきは、ブラジルは日本の23倍の広大な国土と豊富な天然資源を有し、逼迫しつつある世界の資源需要に対し資源供給国としてその国際的な重要性を高めていることである。下の表は、資源・一次産品の生産・貿易における2007年度の世界ランキングを示しているが、ブラジルがいかに資源大国であるかを確認できる。
|
|
生産 |
輸出 |
世界シェア(%) |
|
鉄鉱石 |
1 |
1 |
32 |
|
コーヒー |
1 |
1 |
23 |
|
砂糖 |
1 |
1 |
41 |
|
オレンジ |
1 |
1 |
83 |
|
大豆 |
2 |
1 |
39 |
|
牛肉 |
2 |
1 |
33 |
|
エタノール |
2 |
1 |
80 |
|
鶏肉 |
2 |
1 |
39 |
|
トウモロコシ |
4 |
3 |
10 |
|
豚肉 |
3 |
4 |
15 |
出所:Ministerio da Agricultura e do Abastecimento,
こうした資源輸出に関しては、大豆・食肉・エタノールなどにおける産業コンプレックスの形成によって極めて高い国際競争力を有していることが特徴である。また、資源国として着目すべきは、近年ブラジルの原油生産が急増し純輸出国となったことである。現在の確認埋蔵量は140億バレルとされ、その9割がリオ州沖合の海底油田であるが、海底油田の掘削技術は世界最高の水準を誇り、国営石油公社であるペトロブラスは世界第4位の石油メジャーとなっている。
さらに、ブラジルの経済運営の特徴は、たんにナイーブに経済自由化を推進するだけではなく、80年代の経済危機や99年の通貨危機の経験を踏まえたプラグマティックなマクロ政策を維持するとともに、歴史的にブラジルが抱えてきた貧困や格差問題に対しても現実的な社会政策を実施し、社会的公正とのバランスをとっていることである。このため、中間層の急激な拡大によって国内消費主体の経済構造へと転換しつつあり、持続的な経済成長のための新たなダイナミズムが形成されようとしている。他方、民間部門の変化も著しく、ブラジルが置かれた自然環境や社会的特質を巧みに取り入れ、ガソリンとアルコール(エタノール)のどのような混合比率でも走行するフレックス燃料車や、昨年にJALが購入した中型ジェット旅客機を代表に、ブラジル・モデルともいえる様々な革新を世界にアピールしつつある。外交的にもブラジルの経済的プレゼンスの高まりを背景に、ルーラ大統領は中国、インドを含む途上国グループ(G20)を主導するなど、発展途上国のリーダーとして積極的な外交を展開し、国際的な影響力を強めている
以上のような急激なブラジル経済の変化は、過去30年以上にわたってブラジル経済を研究対象としてきた私にとっては、予想外のことであった。私の学位論文となった研究課題は、1980年から90年にかけてのハイパー・インフレであり、その原因が経済的要因のみならず社会・政治的要因に基づいており、インフレ沈静化がいかに困難であるかが基本的な結論であった。その後、経済自由化がなされたが、貧困・分配問題は解消されず、1999年には通貨危機、2003年の大統領選を目前にした金融不安など、私が観察したブラジル経済は、常に危機的な状況であり、いつまでも「未来の国」であった。しかし、ブラジルはまさに様変わりしており、ブラジルへの再認識を迫られている。
現に、これまでの経験からは国際金融市場に混乱が生じれば、ブラジル経済は必ずといっていいほど深刻な影響を受けてきたが、2008年後半からのリーマン・ショックに始まる国際金融危機に対しては、比較的軽微な影響にとどめており、2009年後半には経済が回復するとの観測が現地では一般的となっている。既に議論した要因に加え、マクロ経済・金融セクターの健全さ、内需主体の需要構成、良好な対外バランス、財政の健全性、過去の危機の経験を活かした適切な政府の対応などの条件がそろっていることが理由だといえる。2009年4月の時点で、既に自動車販売、小売、信用供与などが回復の兆しを示していることから、ブラジルへの国際的機金融危機の影響は限定的であり、現時点の動向をそのまま延長して考える限り、景気の回復は先進諸国と比較して相対的に早い可能性があるといえる。中央銀行の最新のインフレ・レポート(Relatorio de Inflacao - Marco/2009)では、2009年のGDP成長率を1.2%と予測しており、ほとんどの先進国で2009年の成長率予想がマイナスとなる中、ブラジルでプラスの成長率が予想されることは注目に値する。ただし、あくまで予測である。
ここで、ブラジルの株価の変化に関して触れておきたい。以下は、新興諸国である中国、インド、ブラジルと米国と日本の株価の趨勢を、2000年1月を1として示したものである。
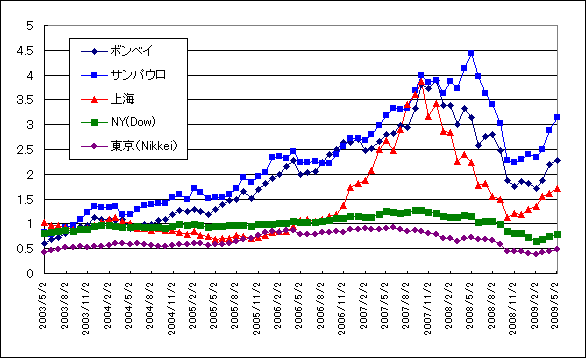
出所:Yahoo Finance
図から明らかなように、インド、ブラジルの株価は2003年頃から、中国のそれは2006年頃から高騰している。米国、日本においても2003年あたりから上昇傾向にあったことが見て取れるが、その程度は新興諸国と比較するとはるかに小さいことが理解できる。わが国においても、これら新興諸国への株式投資ブームとなり、2008年1月時点での投資信託の総額は4.5兆円に達していた(ロイター調べ)。
ブラジルの株式市場でも、国際的金融危機まで株価が上昇を続け、サンパウロ証券取引所の指数であるBOVESPAは、2002年には10,000ポイント前後であったのが、傾向的な上昇を続け、2008年5月にはピークの72,000にまで達した。この間、米国などの先進諸国やその他の新興諸国の株式市場が、サブプライム問題から2007年中頃から低下し始めたのに対し、ブラジルは2008年5月まで株価の上昇が続いた唯一の国であった。国際金融市場の動揺が懸念され始めた時点においても、ブラジルに対する市場の信頼が、依然として継続していたといえる。しかし、2008年9月のリーマンブラザーズの破綻によって、他国と同様に株価が大幅に下落し、30,000近くの値となった。ただし、それ以降は、先進国と比して回復のペースが速く、また、新興諸国のなかで株価の下落の程度はもっとも小さい。2009年5月の時点では50,000近辺にまで回復している。市場は、ブラジルのこれからの成長を信じ、その株価はまだ割安だと判断しているのであろうか。
いうまでもなく、現在のブラジルにおいても、長期的・持続的成長に向けて解決しなければならない課題は山積である。依然として、いわゆる「ブラジル・コスト」が解消されてはおらず、今後の経済成長への制約要因となっている。とくに、様々なインフラの整備、税制・労働などの制度改革、長期資金を提供しうる金融仲介機能の発展、教育制度の改善、治安の改善、官僚機構の効率化、政治制度改革、などが急務であり必須である。こうした改革、改善を通じた経済、産業、企業の生産性向上の必要性とその余地は大きい。また、今後はカウンター・シクリカルな経済政策が必要となると判断されることから、財政規律はこれまで以上に厳密に維持されなければならない。さらに、現時点においても、ブラジルの貧困・分配問題は国際的な標準からみても深刻であり、依然として社会的・政治的不安定化要因として存在している。これまで以上に、経済成長の成果が貧困層に十分かつ速やかにトリックル・ダウンする方策を構築すべきであるし、現在実施されている社会政策をより効果的にすることが必要である。
もちろん、明日のことは誰にもわからない。このコラムが神戸大学経済経営研究所リエゾンセンターのホームページにアップされ、読者がこれを読まれる頃には、事態が急変しているかもしれないし、ブラジルの株価が上昇を続けているかもしれない。ブラジル経済の今後の動向については読者の判断にお任せしたい。
2009年5月11日記